「お金」「時間」のハードルを越えよう
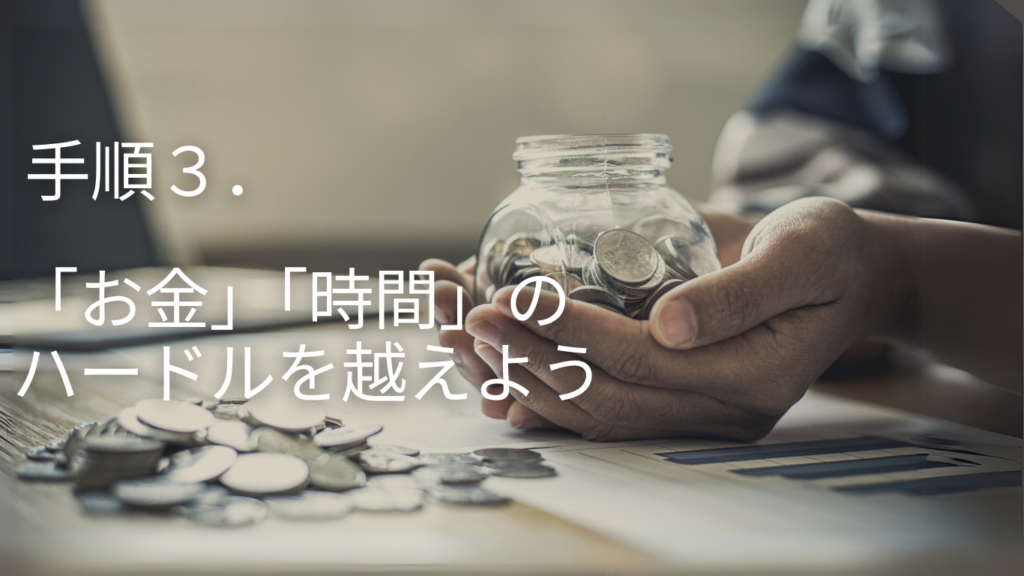
 まぁちゃん
まぁちゃんいよいよ、「お金」、そして「時間」の話ね。どう進めていったらいいかしら?
1.「お金」のハードルを越える
まずは、お金(予算)についてです。
家づくりのために必要なお金の出どころ(資金源)を整理すると、次のようになります。
資金源
・預貯金
・住宅ローン
・国や自治体からの補助金
・資金援助
ここで挙げた資金源を吟味して、どれだけ「お金」を家づくりに活用できるかを考えましょう。



「預貯金」は、人によってさまざまなので、ここでの説明は省くとして・・。
問題は「住宅ローン」ね。
最近、金利も上がったっていう話も聞くし・・。



住宅ローンは、金融機関によって金利も異なるし、返済方法や条件も複数あるから、選択次第で総支払額がだいぶ変わってくる。
だから、いろいろ情報収集をしながら、総支払額が少しでも少なく済むような金融機関選びと返済方法を見極めることが大切なんだ。
住宅ローンを攻略する
住宅ローン・6つのポイント
1⃣ 金利には3種類(店頭金利・適用金利・優遇金利)あり、それぞれ役割が違う
2⃣ 金利のタイプは「変動」「全期間固定」「一部固定」の3種類
3⃣ 返済方式は「元利均等」と「元本均等」の2種類
4⃣ ローン借入時は、元本と金利のほかに、「保証料」と「事務手数料」がかかる
5⃣ 団体信用生命保険(通称:団信)で、万が一の時も住宅ローンがチャラに
6⃣ 住宅ローンを組むと、年末調整でお金が戻ってくる(住宅ローン借入控除)
私たちの場合



ちなみに、僕たちは、(金融機関の安定性は考慮しつつも)総支払額をいかに安く抑えるかを最優先に、ローンを選びました。
うえの6つのポイントでいうと、
2⃣は「変動金利」を、3⃣は「元金均等返済」を、4⃣は「保証料前払いで事務手数料が定額」を選択したよ(5⃣の団信は強制加入)。
保障の特約は特につけてないけど、「口座開設すると金利下げます」的なキャンペーンはフルで入りました。
金融機関から先に選ばないほうがよい?!
住宅ローンを選ぶ際の王道ともいえる選び方が、「契約時の金利が一番安い金融機関を選ぶこと」です。
たしかに、金利が安ければ安いほど、借入額にかかる利子が少額で済むため、最もお得であるようにみえます。
しかし、金利が安い金融機関は、その他の部分で利益を確保する構造にしているところもあるため、総合的に考えることが重要です。
私たちの場合は、当時、変動金利の利率がどこも大差なかったというのもあり、他の条件から選んでいき、最終的に残った中から決定しました。
また、特に注文住宅を建てる人にお伝えしたいのが、「住宅ローンは、契約すれば、必ずしも、支払いたいときにお金を融資してくれるものではない」という点です。
注文住宅は、「契約時」「着工時」「上棟時(中間金)」「引き渡し時」といった、複数回にわたって分割して支払わなければならないところが殆どです。
しかし、金融機関によっては、「住宅ローンは引き渡し完了時の一括払いのみ」と、分割払に対応してくれないところがあります。
さらに、家を建てるための土地を先行して取得した場合、本来は、土地取得費用にも住宅ローンを融資してもらいたいところですが、応じてくれないところもあります。
こういった金融機関と住宅ローン契約を結んでしまった場合、預貯金等でまかなえないとなると、「つなぎ融資」という、「住宅ローンが始まるまでの別の借金」をするしか方法がありません。
つなぎ融資の利率も決して安いとは言えないので、できれば、「土地取得時」や「家の分割払時」にも住宅ローン融資が可能な金融機関を選択しておいたほうが無難です。
このように考えていくと、先に金融機関を決めるより、他の条件から先に埋めていって、残った選択肢の中から選んだほうが、メリットがある場合が多いのです。
住宅ローン・詳細解説



住宅ローンってご存じですか?
住宅ローンとは、住宅用の土地や家屋を購入する際に金融機関から借りる「借金」のことだよ。



やっぱり「借金」なんだ。。(-_-;)
借金っていうからには、1万円借りたら100円余分に払う、みたいな「利子」が発生するんだよね?



そう。
住宅ローンの場合、その利子を「金利」という率(%)で表しているよ。
この金利が高いか安いかで、金融機関に元本(借入額)以外に、余分に払わなければいけない金額の多寡(多い少ない)が決まるんだ。
金利について
金利は、そのときの経済や社会情勢によって変化しています。
住宅ローンは、基本的には、契約時点での金利を用いて計算されます。
金利の種類
金利には「店頭金利(基準金利)」と「適用金利」、「優遇金利」があります。
商品にたとえると、店頭金利は「定価」、優遇金利は「お値引き」、適用金利は「実際の売値」となります。
【各金利の関係】
適用金利=店頭金利-優遇金利
仮に、店頭金利3.5%、優遇金利2.2%だった場合、
X = 3.5% ー 2.2%
X = 1.3%(適用金利)
となります。



つまり、適用金利が重要なのね。
店頭金利と優遇金利はどうやって決まるの?



店頭金利は、次の「金利のタイプ」で説明するよ。
優遇金利は、金融機関が個々の基準で設定しているもので、借りる個人の支払い能力をみて決めるんだ。



個人で変わるの?



そうなんだ。住宅ローン審査の際に決まるよ。
優遇金利は、借入人の職業・自己資金・その他の借入状況(例:車のローン、カードローン)など、人によって変わります。



優遇金利は人によって変化するものだから、表立った表示は少ないよ。
インターネット上では店頭金利からの最優遇金利(最も金利引き下げ幅が大きい)を差し引いた後の「適用金利」が、
「金利:0.65%〜」
のように表示されていることが多いね。
金融機関によっては、次のような条件で優遇金利の引き下げ幅を拡大することも可能です。
- 指定のクレジットカードを契約する
- 指定の金融アプリをダウンロードする
- 金融機関が薦める金融商品を購入する
- 住宅ローンの引落口座に設定する
優遇金利は、契約時から終期まで一定の「通期優遇」タイプもあれば、期間の途中で優遇金利幅が縮小される「当初優遇」タイプがあるため確認が必要です。「当初優遇」タイプは、次の「金利タイプ」で説明する「固定金利期間選択型」に多く見られます。「当初優遇」タイプは、一定期間経過後に、優遇幅が縮小されるため、繰上げ返済や将来の借り換えを予定されている場合に有効です。



つづいては、金利タイプについて見てみよう。
金利タイプは、借入期間中の利率の変化の仕方で、次の3種類に分けられるよ。
金利タイプについて
・変動金利
・全期間固定金利(フラット35)
・固定金利期間選択型



「変動金利」は、金利が社会情勢によって変化するタイプ。
「全期間固定金利」は、金利がずっと変わらないタイプ。
そして、「固定金利期間選択型」は、最初の3年、10年など数年間は固定金利で、一定期間を過ぎると、変動金利に変わるタイプね。
店頭金利は、この3つのタイプで変わってくるみたいだけど、どちらがお得なのかしら?
変動金利と固定金利で、金利決定の際に見る“ものさし”が違う
変動金利と固定金利(金利期間選択型を含む)では、店頭金利の決定方法が異なります。
【店頭金利の決定方法】
「短期プライムレート(金融機関が業績が最も良く信用できる企業にお金を貸し出す際の『最優遇貸出金利』のうち、1年以内の短期貸出金利のこと)」に+1%したものを店頭金利にしている金融機関が多い。
この短期プライムレートは、日銀の政策に大きく左右される。
日銀は長い間、企業がお金を借りやすいよう、マイナス金利政策など、短期プライムレートを低めに設定していた。しかし、2024年に入り見直しの方針を固め、利上げに踏み切った。



要は、企業にお金を貸し出す際「少し利子をつけても借りてくれるだろう」という判断に変わってきたということ。今後、この短期プライムレートが上がっていくと、連動して変動金利も上昇していくため、日銀の政策は、ニュースやネットで情報収集しておくべきだね。



でも、日銀は国民の大顰蹙(ひんしゅく)をかってまで、金利を急激に上げたりするかしら。そんなことをしたら、企業が金融機関からお金を借りづらくなってしまうし、変動金利で住宅ローンを借りている人も多いっていうのに…。
住宅金融支援機構の2022年4月調査によると、
変動金利型は73.9%
固定期間選択型は17.3%
全期間固定型は8.9%



住宅ローン利用者の約3/4が変動金利なのね。
【125%ルール】
変動金利(元利均等返済方式)には「125%ルール」というルールが存在する。これは、万が一、急激に短期プライムレートが上昇したとしても、金利改定は半年に一度で、金利の上昇幅も前回比最大125%に抑えるというルールである。但し、この「125%ルール」には落とし穴があるので要注意(次の「返済方式」にて解説)
固定金利
【店頭金利の決定方法】
10年国債利回り(国が発行する債券で、償還(返済しなければならない)期間が10年のもの)が基本で、企業ではなく投資家の動きによって大きく左右される。投資家が「今後金利が上がりそう(儲かりそう)」と思えば10年国債の利回りは上昇し(つまり、固定金利が上がる)、「儲からなそう」と思えば借入が減るので国債利回りは下がる(つまり、固定金利が下がる)。
短期プライムレートに比べ、国際利回りは変動が激しい



固定金利は、元となる指標自体は変動金利より値動きが激しいのか…。契約時の金利がそのまま一定期間適用されるのが固定金利だから、契約時の店頭金利が総支払額に大きく影響するってことだね。



住宅ローン契約のタイミングが超重要っていうことね…(-_-;)
固定金利のほうが変動金利より上下動が激しいため、金利の上昇局面においても、必ず固定金利から先に上がり、後追いで変動金利が上がっていきます。変動金利で借り入れを行っている場合、固定金利の動向を参考にするとよいでしょう。
変動金利と固定金利では、現在は、変動金利のほうがお得
2024年時点で、ゼロ金利からプラスに転じたことで、金利も緩やかな上昇局面にあると言えます。
しかし、変動金利が急激に上昇し、固定金利よりも総支払額が増加する、といった状況になるのは、もう少し先の話になるでしょう。なぜなら、景況感が大きく改善しない状況下で、変動金利の拠り所となる短期プライムレートを政府がすぐに高い水準に引き上げるとは想定しづらいからです。
もし、この短期プライムレートが固定金利の利率を上回るレベルに達したとしたら、日本経済はかなりの好循環の過程にあるか、バブル経済に近い状態にあるのかもしれません。そういった予兆が垣間見える場合は、フィナンシャルプランナー(FP)さんや金融機関の窓口に行って相談をするとよいでしょう。



「先に動いたもの勝ち」。相談するなら早めがいいですよ。
借入金額が大きく、返済期間が長めの場合は、支払う利子も多額ですので、金利上昇に備えた対策はしっかり行っておくべきです。
返済方式について



返済方式は、次の2種類。
・元利均等返済
・元本均等返済
元利均等返済方式について
- 元利均等返済方式
-
金利が一定であれば、月々の返済額が変わらない返済方式。返済額が一定のため、返済計画が立てやすいというメリットがある。多くの金融機関で薦めているのは元利均等返済方式。
【メリット】
・返済額が一定(金利が変わらない場合)【デメリット】
・総支払額が元金均等返済より多い【備考】
・(変動金利の場合)急激な金利上昇時も半年間は金利据え置き。上昇しても125%まで - 元本均等返済方式
-
金利ではなく、毎月支払う「元金」が変わらない返済方式。「元金」とは、借入額のうち、利子分を含まない部分のこと。通常、「住宅ローンで4000万借りた」と言ったら、「4000万円」が元金である。この元金を借入期間で均等割して返済するのが元金均等返済方式である。
【メリット】
・総支払額が「元利均等返済」より少ない【デメリット】
・月々の返済額が上下する【備考】
・(変動金利の場合)半年間の金利据え置きや、125%ルール適用対象外



「うちは元金均等」なんでしょ?
元金均等返済方式は、金利据え置きや125%ルールが適用されないってあるけど大丈夫?



日銀が、利上げを過激に行わないと踏んで元金均等を選択してます(笑)。
ちなみに、元利均等は、利子から優先して返済されていくという仕組みなんだ。だから、元金の返済がなかなか進まず、総支払額も元金均等よりけっこう大きくなってしまう。
一度、住宅ローンの返済シミュレーションで「元利均等」と「元金均等」で比較するとわかりやすいよ。
そして、僕が元利均等を選ばなかった理由の極めつけが「125%ルール」。これは、金利が急上昇しても、125%までしか支払いの義務がない、というルールではないんだ。



ええっ?そうなの?!



元利均等は、金利急上昇時に、「その時点」での支払額の上限が125%になるに過ぎず、125%を上回った分については、最終返済時にまとめて請求される仕組みなんだ。



ぎょぎょっ?!
【125%ルールの注意点】
125%ルールは、金利の見直しも半年に1回で、金利急上昇時も、最大前回比の125%に抑えられるというルールであり、借入者にとって安心感があるように見える。しかし、借入者が金利が上昇した分だけ支払うというルールに変更はない。つまり、実際の金利上昇幅が半年で前回の2倍(0.5%から1.0%に上昇)となった場合、125%ルール適用で、金利は0.5%から0.625%までしか上がらない。しかし、最終的には、金利1.0%分の利子分も払わなければならず、1.0%-0.625%=0.375%分の利子を、住宅ローン返済の最後に支払わなければならない。



一応、制度上はそうなってるよ。
日本は、過去のバブルの教訓もあるし、よほど経済が上向かない限り、そんな急激な利上げはしないんじゃないかな〜と思うけどね。



ただし、こればっかりは私たちも予言者ではないので確実なことは言えないよね。いろいろな情報を頼りに、最終的には自己判断で決めていくしかないですね。
その他
住宅ローンには、その他にもいくつか気をつけたいポイントがあります。
- 保証料
- 事務手数料
- 団信(団体信用生命保険)
- 保障の特約
- 住宅ローン借入控除



住宅ローンて考えなきゃいけないことがいっぱいあるのね…。
- 保証料について
-
保証料とは、借入者が住宅ローンの返済ができなくなった場合に、保証会社が金融機関に借入残金の支払いを代行する際の対価として住宅ローンに上乗せで支払うもの。
最近は、保証料0円の金融商品も多い。ポイント
・保証料は繰り上げ返済の際、戻し保証料として戻ってくる
・保証料0円だけで「お得」と判断するのは危険(事務手数料等に転嫁されている可能性がある) - 事務手数料について
-
住宅ローン契約手続きの際に支払う手数料。融資手数料と呼んでいる金融機関もある。
事務手数料は「定率型」と「定額型」がある。
借入額が大きいと、定率型の場合、事務手数料が高くなる(例えば、4000万円借入額の2.2%が事務手数料だった場合、事務手数料は88万円にもなる)。一方、定額型の場合、事務手数料は安いが、その分「保証料」を別に設けているケースが多い。
なお、繰り上げ返済時に、保証料として支払った金額は「戻し保証料」として、期間短縮された返済額に応じた金額が返金されるが、事務手数料として支払った金額は、一切返金されない。
ポイント
・「繰り上げ返済」を前提で借りるなら、保証料が有料だったとしても、事務手数料は「定額型」がお薦め! - 団信(団体信用生命保険)について
-
団信(団体信用生命保険)とは、借入者が死亡または高度障害状態になった際、住宅ローンの残高が0円になる保証制度。現在、住宅ローン契約時に一緒に加入するケースが殆ど(強制加入の金融機関も)。



僕に、万が一のことがあっても安心だ。
- 保証の特約
-
「3大疾病特約」など、万が一、主な死亡原因で特約対象になる疾病に罹患した場合などに、住宅ローン残高が0になる保障の特約制度。「特約をつける分、金利を0.03%上げます」という金融機関が多い。
ポイント
・健康不安があり、心配だという人は特約をつけてもいいかもしれないが、その分総支払額が増えることをふまえること。
・特約は、住宅ローン借入期間に「がん」「心筋梗塞」「脳卒中」など特約対象の疾病と診断されないと適用されない。「食事」「睡眠」「運動」など健康づくりに気をつけることで、ある程度のリスクを減らすことはできる。 - 住宅ローン借入控除
-
住宅の新築時、家が完成した年の年末調整分から住宅ローン控除の申請が可能になり、税金の控除が受けられる。
控除額・・・住宅ローン借入総額の0.7%(2024年時点)
※住宅ローン借入控除は、控除初年度の税制が適用される。税制は年度ごとに見直され、控除額の見直しも行われる。



5000万円の借入を行った場合、5000万✕0.7%=35万円が年末調整※で戻ってくるのね。
これからの施主たちのためにも、いつまでも継続してほしいな…。
※収入額等によって、住宅ローン控除の上限額が変わることがある


例えば、現在の変動金利が0.5%なら、
0.5% < 0.7% だから、
1年間に支払う利子分より、住宅ローン控除で戻ってくる金額のほうが大きいことになるよ。「繰り上げ返済」で積極的に借入金額を減らし、総支払額を抑えるのも1つの手だが、総支払額の減少に伴い、住宅ローン控除額も減少してしまう。
変動金利が住宅ローン控除の利率を超えないうちは、住宅ローン控除額が大きいほうがお得になる可能性が高いため、繰り上げ返済のタイミングを住宅ローン借入控除終了後にまとめて行うのも一つの方法である。
ポイント
・住宅ローン控除の恩恵を受けられる間は、利子分は控除でカバーできる可能性がある
住宅ローンのリスクヘッジ法



いやはや、やっぱり住宅ローンって借金なんだから、どうにかなっちゃったら怖いよー。



リスクヘッジするなら、この2つを検討するといいよ。
- 繰上げ返済をする
- 景気上昇局面で儲かりそうな金融商品を買う
- 繰上げ返済をする
-
繰上げ返済とは、月々の住宅ローンを返済しながら、コツコツ預貯金を貯め、月々の返済とは別にまとまった額のローンの返済を行い、ローン支払残額を減らすこと。リスクヘッジの手段としては、最も現実的で手堅い方法。繰り上げ返済手続きは、一昔前までは金融機関窓口で行わなければならなかったが、現在は、多くの金融機関でスマホからの電子決済手続きが可能になっている。住宅ローンの一部を繰り上げ返済する一部繰り上げ返済であれば、電子手続きの場合手数料が無料になるので、預貯金がある程度貯まってきたら、逐一繰り上げ返済が可能。ただし、住宅ローン控除との絡みもあるので、返済のタイミングは検討すべき。
ポイント
・繰り上げ返済最大のメリットは、利子の支払が減るため、総支払額を減らせること。返済期間を短縮する期間短縮型と、毎月の返済額を減らす返済額軽減型がある。同じ繰り上げ返済額でも、期間短縮型のほうが、総支払額を減らすことができる。 - 景気上昇局面で儲かりそうな金融商品を買う
-
住宅ローンの上昇率以上に、儲けが大きそうな金融商品を購入し、もし、住宅ローンが急上昇した場合でも、金融商品の利鞘(りざや)を利用し、返済を補填する方法。日銀の金融政策は国策であり、もし、国策で金利が上昇しているのであれば、国内の金融市場も活発であり、金融市場でも利益を生みやすい状況にある。株式や為替等の金融商品を同時購入し、将来の金利上昇時に備えれば、万一のときの対策にもなるし、資産形成にもつながる。
但し、必ず補填が担保されるものではないし、損失のリスクが伴うものでもある。そのことを理解のうえ、検討することをお勧めしたい。



いわゆる「投資」と呼ばれるものは、知識や情報収集力、経験がものを言う世界。なかなか素人が手を出しにくいのも事実。



そういうときは、FP(フィナンシャルプランナー)の無料相談などを利用してみるのも手ね。後は、独学で学ぶか…(苦笑)
住宅ローンまとめ
住宅ローンを借りる際、「安心」を重視して、手堅く「固定金利」で借りたとしても、結果的に総支払額が増え、多額の利子を支払ったという状況は避けたいところです。
住宅ローンを必要以上に恐れず、情報収集やFP無料相談などを活用して不安のたねを取り除き、賢く活用していきましょう。
補助金(助成金)を活用する
住宅ローンは、「いかに損をしないか」といった、どちらかというとネガティブな話でしたが、ここからは、ポジティブな、得する話をしていきましょう。
実は、家を建てると、国や地方自治体からの補助金(助成金)がもらえることがあります。これをフル活用することで、建築費用を抑えることができます。



東京都で建てた場合の、新築の戸建住宅に対しての主な補助金(助成金)はこちらです。
活用できる主な補助金
| 補助金(助成金)名称 | 最高補助額 | 申請先 |
|---|---|---|
| 東京ゼロエミ住宅 | 240万円 | 東京都(環境局) |
| 長期優良住宅 | ― ※1 | 国(国土交通省) |
| ZEH(ゼッチ)住宅※2 | 125万円 | 国(国土交通省) |
| LCCM住宅整備推進事業 | 120万円 | 国(国土交通省) |
| 子育てエコホーム支援事業 | 100万円 | 国(国土交通省) |
| 地域型住宅グリーン化事業※3 | 140万円 | 国(国土交通省) |
※1 長期優良住宅は、税制等の優遇制度であり、補助金等の支給はなし
※2 ZEHには、認定条件によって複数の基準があるため、最高額のZEH+の基準を掲載
※3 2023年度まで。2024年度は募集なし



全国の補助金情報も、追って掲載予定なのでお待ちくださいね。



ちなみに、僕たちの家は、上の表の緑のアンダーラインを引いた補助金(助成金)を全て利用することができたよ。
補助金がもらえる条件
もちろん、どんな家を建てても補助金がもらえるわけではありません。
現在は「地球環境にやさしい、高性能で省エネルギーな住宅を建てた場合」に適用されるものがほとんどです。
また、各補助金には、両方の補助金がもらえる「併給」可能なものと、どちらか一方しかもらえないものがあります。



基準を満たせば全ての補助金がもらえる訳じゃないのね・・
東京都の助成金制度「東京ゼロエミ住宅」を利用すれば、太陽光発電などその他の助成と合わせると、なんと「最大385万円」もの減額に?!
子育て系の補助金制度※と組み合わせれば、なんと!500万円近くもお得に家が建てられる!
※2024年度の事業名称は「子育てエコホーム支援事業」



この、大型助成金制度については、
「東京ゼロエミ住宅『最高水準A』の家を、アイ工務店で建てたらこうなった」にて解説してるよ。
詳しくは、上のバナーをクリックしてね
他の道府県で家づくりを検討されている方も、独自の制度を設けているところも多いので、情報を集めて、積極的な活用を検討してみましょう。
資金援助について
感謝の気持ちを忘れずに
家づくりはとても高い「買い物」です。また、昨今の少子高齢化の進展に伴い「共働き世帯の増加」や「上がらない給料」など、勤労世帯にとって向かい風の状況が続いています。そのような状況もあいまって、両親から、「資金援助」の話をもらうこともあるでしょう。
それは「非常に有り難いこと」です。
そういった機会はなかなか求めて得られるものではありませんが、もし、資金援助の話をいただき、家づくりを進められるのであれば、感謝の気持ちをもって、いただいたお金を精一杯有効活用するようにしましょう。そして、親孝行をいっぱいしてあげてください。



子どもの幸せを願わない親はいないから、私たち自身も幸せで、そして元気な姿を見せられるようにしなきゃね。
「住宅取得等資金にかかる贈与の非課税制度」を利用しよう
通常、両親を含む周りの人からお金をもらう場合、年間で基礎控除額110万円を超える分については、「贈与税」という税金が発生します。
しかし、「住宅取得等資金にかかる贈与の非課税制度」を使った場合、直系親族(実の親)からの贈与であれば、最大1000万円まで非課税で受け取ることが可能です。
この制度を活用し、親からの資金援助を少しでも家づくりに役立てられるようにしていきましょう。
共有名義という裏技
また、仮に「親から2000万円まで資金援助してもらえる」となった場合について考えてみましょう。
この場合、上記のうち、住宅取得等資金の贈与に該当する1000万円と、基礎控除額110万円を非課税で受け取ったとしても、残りの890万円には「贈与税」がかかってしまいます。
このときに発生する贈与税額は、
贈与税額 = 890万✕30%(贈与税率)― 90万(直径親族からの特例贈与財産の場合)= 177万円



177万円も…?!
つまり、2000万円の親からの贈与(資金援助)に対し、贈与の特例措置を利用したとしても、177万円を税金として納めなければならないことになります。



納税は国民の義務とはいえ…大変だ(-_-;)
このとき、「親との共有名義で家を建てる」という方法があるのをご存じでしょうか。
例えば、「家を4000万円で建てる」資金計画が立てられたとします。
うち、親からは2000万円の資金援助をしてもらえることになったのですが、贈与税非課税は基礎控除分を含めても1110万円まで。
このような場合に、2000万円から1100万円を差し引いた890万円を、贈与でもらうのではなく、「親名義」のまま、新築住宅を共同購入するのです。
≪住宅購入名義≫
親名義〈890万〉 + 自分名義〈3110万〉 = 4000万
ちなみに、登記簿上も、親と自分の共有名義となるので、このような所有形態となります。
≪登記簿上の持分割合≫
持分割合(親) ・・・890 / 4000
持分割合(自分)・・・3110 / 4000
このようにすると、贈与税等の税金は一時的に発生しなくなります(勿論、住宅取得等資金の贈与非課税分にかかる確定申告は必要です)。
但し、税金が今後一切発生しないかというと、そうではありません。家屋の共有名義人となった親が亡くなったときに、親名義の共有分[建物評価額 ✕ 890 / 4000]が相続税の計算対象になります。
しかし、相続税にも基礎控除額があり、相続財産から次の控除額が差し引かれます。
相続税の基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 ✕ 法定相続人の数)
また、相続税というのは、亡くなられたときの時価で計算されます。
建物は、新築時を頂点として経年で資産価値が下がっていく仕組みのため、相続時には、取得時より建物評価額も下がっているのが通常です。
このように考えると、相続税が基礎控除の範囲内に収まり、結果的に、納税義務も免除される可能性が高まります。



親の相続とか、あまり考えたくはない問題だけど…



たしかに。でも、親からいただいた資金を無駄にしない努力も、親孝行の1つかなと思う。
予算の上限を見積もる
最後に、今まで検討してきたなかで、おおよそどの程度、家づくりに拠出することが可能かを考えましょう。
・預貯金
・住宅ローン
・補助金(助成金)
・資金援助
上記を元に、2つのボーダーを設定します。
1つ目のボーダーは、「この程度の予算に抑えたい」という、無理のない「理想の予算」。
2つ目のボーダーは、「無理すれば、ここまでなら出せる」という「予算の上限」です。
ここで、大切なことは、「予算の上限は、本当の上限額にせず、多少のバッファを持たせる」ということです。
いざ、家づくりが始まると、あれもこれもと欲張り、いつの間にか「理想」よりも「予算の上限」に照準を合わせた選択になってしまいがちです。
特にお子さまのいる世帯の場合は、子どもの成長に合わせた出費も考えなければなりません。
家づくりで多額の住宅ローンを組んだ結果、後で首が回らなくなるなんてことのないように、「上限額」にもある程度の余裕をもたせ、無理なくやりくりできるようにするのが賢明です。
大切なのは「情報収集」と「あきらめない心」
家づくりを検討するなかで、「お金」の問題がネックで、諦めたり、家族の理想像を「下方修正」したりされる方は多いと思います。
このとき、その状況を打開してくれるのが、「情報収集」と「あきらめない心」です。
幸い、昨今のインターネット技術の発展により、昔とは比べものにならないほど情報収集力が向上しています。また、スマホの登場により、時間・場所を選ばずに「お得な情報」や「有益な情報」を調べられるようになりました。
さらに、SNSの普及により、個人からの発信が増えたことで、気軽に人知を借りながら解決策を見つけやすくなっています。これに、AI技術が加わり、今後、ますます情報収集の可能性が広がる社会になってくるでしょう。
このような社会では、「情報収集力の差」が、結果に直結するようになってくるのです。
便利になってきたとは言え、情報収集には、根気強さも必要です。
情報収集力をフル活用するためにも、目的を達成するまでは決してあきらめない気持ちも必要です。
この2つの力が備わっていれば、「お金」の問題だって、きっとよい打開策が見つかるはず!
このブログのみならず、様々な情報をフル活用して、最大限に「お金」を活用して家づくりを成功させてくださいね!



家づくりに有効なお金の活かし方で、「こんなのもあるよ」といった情報提供があれば、お願いします。
皆さんの家づくりのために、こちらでも紹介できればと思います。



いやー…お金の話、長かったー!



そうね(笑)。お金は、専門用語も多いから眠くなっちゃうよね。
みなさんは、少しは、お金のやりくりの目途はつきましたか?
2.「時間」のハードルを越える
引っ越し時期が決まっているか
家づくりで「時間」が問題になるとすれば、それは、「引っ越し時期」との絡みです。
引越しの時期がある程度決まっている場合、家づくりにも少なからず影響を与えます。
すぐに引っ越しが必要な場合
この場合、2〜3か月後にはお引越しということもあるでしょう。
実は、注文住宅で家づくりを行う場合、検討のスタートから完成(引っ越し)まで最低1年は見ておくとよいでしょう。
そうなると、すぐの引っ越しには到底間に合いません。



家探しを始めてすぐの、何も知らなかった頃、
「半年後には注文住宅が建つ!」なんて本気で思ってたもんな…



ご冗談を(笑)
一方、中古住宅や、完成済みの建売住宅やマンションに空きがある場合、2〜3か月もの期間があれば引っ越しは可能です。
時間がかかってしまうなら、注文住宅はあきらめて、建売か中古住宅を探そう
家の検討で、時間の制約を第一に考えてしまう場合、このような考えに陥るのも無理もないことです。
しかし、引っ越しを急がなければならない時でも、転勤などの諸事情を除けば、注文住宅での家づくりは可能です。



そんなことってできるの?
その方法とは、引っ越し先の土地で、いきなり住宅を「買う」のではなく、まず「借りる」のです。
具体的な流れですが、下のようになります。
- 引っ越し先のエリアを決める
- ネット又は不動産会社で賃貸物件を検索し、決まったら、不動産賃貸契約を結ぶ
- お引っ越し
- 賃貸住宅に住みながら、将来の家づくりのための計画を立てる
- 新築家屋の工事スタート
- 建築中
- 完成~引っ越し
上記のように進めていければ、「家族の理想」を我慢して、焦って住み替えをする必要がなくなります。
賃貸住宅を探す際に、1点気をつけたいのは、学校に通う子どもたちがいる場合です。



仲のよい友達と離れちゃうのがツラいよう・・
【子どもの学区変更は最小限に】
賃貸住宅へ引っ越し、その後、家の完成後に再度引っ越しとなった場合、小学校に通う子どもの「学区」が変わる場合、転校を2度もすることになり、子どもに心理的負担をかけることになってしまいます。
引越しをするときは、将来住みたい土地をあらかじめ見定めておいたうえで、同じ学区にある物件から選ぶようにしましょう。
時間の余裕がある場合
注文住宅で家を建てる場合、動きだしてから家の完成まで、最低でも1年以上の時間を要します。まずは、「家づくりは時間がかかるものだ」という想定で動くことが大切です。



子どもの転校がなかったとしても、引っ越しは一大行事だから、忙しい時期は避けたいところね。



でも、夏休みとかが引っ越しでつぶれちゃうのはヤダな〜
ハウスメーカーにも、引っ越しの目安時期については、あらかじめ、契約前の段階で伝えておくことをお勧めします。
そのほうが、ハウスメーカー側もその後の工程を管理しやすいからです。
ハウスメーカーの営業マンは、私たちだけではなく多くの人の家づくりを同時並行で行っています。
このとき、家づくりの時期(特に、着工後の工程)が集中してしまうと、現場に負担がかかり、いろいろな工程に影響を及ぼしてしまい、調整が難しくなります。
子育て世帯の引っ越しは、「春休み」に集中する
新婚さんであったり、子どもが小学校入学前、または、子どもがある程度大きくなっている等であれば、引っ越し時期の範囲が広くとれるのですが、子育て世帯の場合、子どものためにも「学年が変わる「3月修了式(卒業式)~4月始業式(入学式)」の間に引っ越したい」と考える人が多いでしょう。
他にも、仕事においても4月は新年度にあたるため、3月中旬~4月上旬までの1か月弱の期間は、どうしても引っ越しが集中します。
このとき、気をつけたいことの1つめが、「建築会社が対応できるか」という問題です。



建築会社には、かなり早めに「3~4月の新学期までに引っ越したい」と意思表示しておいたほうがいいよ。
実際、建築工事作業員の確保の問題で、春休みシーズンを前後しての完成ということも十分あり得ます。このような場合も事前に想定して、「年度途中での転校も止む無し」とするのか、「完成後も、春休みまで引っ越しを先送りする」か、はたまた「引っ越し先の学区のアパートに一時引っ越ししてから完成後引っ越す」か、など検討を進めておくとよいでしょう。
気をつけたいことの2つめが、「引っ越し業者の手配」の問題です。
春休みは、一年のなかで最も人気のある、引っ越しの「ハイシーズン」にあたります。
このため、引っ越し業者の相談は、早いに越したことなく、直前の相談だと「引っ越し業者を予約できない」「割高な引っ越し料金を払わざるをえない」ことになります。
相談は、早めに行いましょう。



ただ、引っ越し相談は、「引っ越し日」と「持ち運ぶもの」を事前に決めておかないといけないの。



引っ越し日は、工事の進み具合でもズレる可能性もあるし、持ち運ぶものを決めるには、家の整理も進めなければいけない。
けっこういろいろと、「やらなきゃいけない」「決めなきゃいけない」ことがあるんです。

![東京ゼロエミ住宅「最高水準A]の家をアイ工務店で建てたらこうなった](https://tokipa-awesome.com/wp-content/uploads/2025/01/1ce3a03821a2352ab1045faf02975650.png)